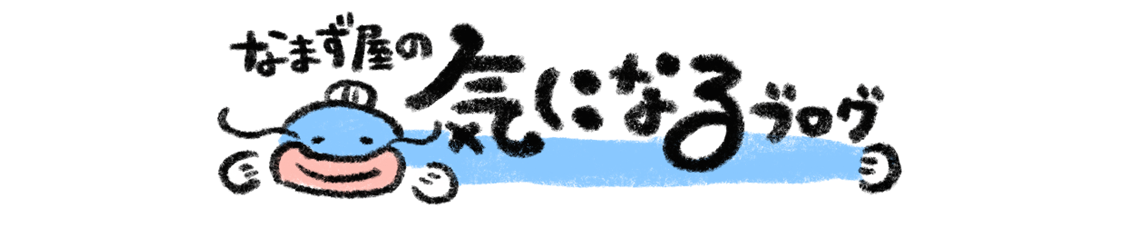ブログを書き始めるときに書き出し方に困ったことありませんか?
- 導入文が思い浮かばないから記事作成に時間がかかる…
- 書きたいことはあるのにどういう順番で書いていけばいいかわからない…
特にブログを始めたての頃ってこの悩みに必ずぶち当たりますよね。
何もわからないときって、勢いで導入文を書いてしまうのは、みなさん通る道だと思います。
では、どうすれば導入文をスラスラと書けるようになるのでしょうか。
それは、4つのポイントをおさえることで解決します。
この4つのポイントが頭に入っていることで、
- 導入文で手が止まりにくくなる
- 導入文が苦手じゃなくなる
といったメリットがあります。
ぜひ最後まで読んでみてください。
それでは解説します。
導入文で大事なこと
記事の書き出し、つまり導入文でその後の記事を読者が読むかどうかが決まります。
ポイントは、
- 導入文でシンプルに伝える
- 記事の本文で具体的に伝える
です。
大事なことは、読者がかかえる悩みをこの記事なら解決してくれそう、と感じてもらうことです。
悩みを解決してくれそうと感じてもらいやすい導入文のポイントは、
- 読者の悩みに対する問いかけ
- 悩みを整理する
- 解決策の提示
- 解決策に対する不安の潰しこみ
の4ステップで文章を書いていくことです。
それぞれ解説します。
読者の悩みに対する問いかけ
シンプルに言うと、冒頭で『〇〇で悩んでいませんか?』と問いかけることです。
もちろんこれだけでは、読者がその後の文章に引き込まれることはありません。
なので、悩みの内容を深掘っていく必要があります。
この深掘り次第で読者が記事に対して、『私の悩みを理解してくれている!』と感じるかで成果が変わります。
例えば、
ブログを書くときに導入文を考えるのって苦労しませんか?
何を書いたらいいかわからない…
この表現で読者に読んでもらえるのかな…
最初の文章で読むのをやめられたらどうしよう…
のような具合です。
このように想定する読者の脳内ボイスを冒頭で表現することが大切です。
悩みを整理する
このSTEPでは読者がなんとなく感じている不安を整理し、言語化します。
この言語化した不安・悩みの解像度が高ければ、読者は一気に記事に引き込まれます。
さきほどの続きを例にしてみましょう。
導入文を書くのってけっこう難しいですよね。
何を参考にしていいかもわからないし、難しく書きすぎると読者に伝わらないし、興味を持ってもらえなかったら、あとの文章も読まれないですからね。
ブログに慣れないうちは悩ましい問題のひとつです。
読者の悩みを具体的に表現することで『自分の悩みはこういうものだったのか』という気づきを感じてもらうことが狙いです。
解決策の提示
このSTEPでは読者の悩みに対する解説策を伝えます。
この解決策の意外性や簡単さなどで読者の期待値が変化します。
期待値を上げすぎず、下げすぎず、絶妙なラインを狙いましょう。
それでは例文です。
でも、これらの悩みは導入文のコツをまだ知らないから起こるって知ってましたか?
導入文のコツを知らないのは、ヒートテックだけで南極へ行くようなものです。
しっかり極寒仕様の装備を準備していきましょう。
現状がどれだけ困る状況かを何かに例えるとイメージが伝わりやすくなります。
色々なパターンを試してみましょう。
解決策に対する不安の潰しこみ
最後のSTEPです。
ここでは解決策に対する不安に対して先手を打っておきます。
基本的に難しかったり、再現性のないものは読んだ後にがっかりされるので、あまりおすすめしません。
それでは、例文です。
もちろん『コツ』というぐらいなので難しいものではありません。
理解さえしてもらえれば、誰でも実践できます。
今まで70人にこのやり方をやってもらいましたが、70人ともしっかり実践できています。
なので、不安にならなくても大丈夫ですよ。
それでは、解説していきます。
できることなら、数字の根拠を入れるとより一層、読者の不安を和らげることができます。
例文をつなげると…
これまで使った例文をすべてつなげて確認してみましょう。
ブログを書くときに導入文を考えるのって苦労しませんか?
何を書いたらいいかわからない…
この表現で読者に読んでもらえるのかな…
最初の文章で読むのをやめられたらどうしよう…
導入文を書くのってけっこう難しいですよね。
何を参考にしていいかもわからないし、難しく書きすぎると読者に伝わらないし、興味を持ってもらえなかったら、あとの文章も読まれないですからね。
ブログに慣れないうちは悩ましい問題のひとつです。
でも、これらの悩みは導入文のコツをまだ知らないから起こるって知ってましたか?
導入文のコツを知らないのは、ヒートテックだけで南極へ行くようなものです。
しっかり極寒仕様の装備を準備していきましょう。
もちろん『コツ』というぐらいなので難しいものではありません。
今まで70人にこのやり方をやってもらいましたが、70人ともしっかり実践できています。
なので、不安にならなくても大丈夫ですよ。
それでは、解説していきます。
これが完成形です。
まとまっている印象を受けませんか?
ぜひ今回ご紹介した導入文作成フローにそって書いただけです。
慣れれば、導入文をサクッと書くことができるので、ぜひ実践してみてください。
もっと楽に導入文を作成する方法
ここまでは自分が書くための方法を書きましたが、もっと簡単に導入文を作成する方法があります。
それは文章生成AIを活用することです。
私が使っているのが、
- ChatGPT
- Catchy
の2種類です。
ChatGPTはアメリカ発の企業、OpenAIが開発した人工知能チャットボットです。
文章を入力するだけで、答えを返してくれます。
無料プランと有料プランがあり、有料プランの場合月額20ドルです。
気になる方はこちらからどうぞ。
一方、CatchyとはChatGPTの技術をベースに、日本人が開発したAIアシスタントライティングツールです。
Catchyのいいところは、
- たった4STEPで簡単に記事作成できる
- Proプランなら無制限に文章を生成できる
- 無料プランを含む、初心者からヘビーユーザーまで満足できるシンプルな料金プラン
です。
記事作成を少しでも時短したい方にはChatGPTと共に必須のツールです。
少しでも気になった方はこちらの記事で詳しく解説していますので、よろしければご一読ください。
せっかく内容は思いついたのに文章が思いつかない…キーワードは出てくるのに文章にすると文字を入力する手が止まる…いっそのこと誰か代わりに書いてくれ…文章を考えるのに必死につくった時間がだんだんとなくなっていく経験はあ[…]
サクッとリンクで飛びたい方はこちらのボタンからどうぞ。
まとめ
読者の悩みを解決する順番は、
- 読者の悩みに対する問いかけ
- 悩みを整理する
- 解決策の提示
- 解決策に対する不安の潰しこみ
楽に導入文を作成したいときは、
- AIを活用する
今回紹介した内容を知り、実践することで記事の書きやすさが全然違ってきます。
特に読者の悩みを解決する順番は不変のものなので、ぜひとも活用してみて下さい。
最後に
もっとブログの書き方を学びたい!という方にはこちらの記事を用意しています。
この記事ではブログを書くときに意識すべきことを紹介しています。現在のテーマ数は6個、おまけ1個です。最終的にはテーマ数を13個まで増やす予定です。書きあがり次第、順次この記事にアップしていきます。早速、ブロ[…]
ブログの書き方について色々なテーマで紹介しています。
ぜひ参考にしてみてください。
この記事があなたのお役に立てれば幸いです。
ではまたっ!